大正100年のmasterpeice -代表作を巡る-
2012年9月1日開設
詩歌
詩だけではなく、短歌、俳句などの短詩型文学、歌謡などもみていけたら、と考えています。
特に、明治の終りから大正の初めにかけては、詩人の活動が活発でした。そのなかでの夢二の位置を探りながら、独自な探究を試みます。

竹久夢二色紙〈宵待草に題す〉大正9年頃 (三鷹市蔵)
(画像は、『「宵待草」ノート -竹久夢二と大正リベラルズ-』表紙より)
「宵待草」が大正期を代表する歌であるといえば、頷く人も少なくないでしょう。
ですが、「宵待草」を収録した『どんたく 絵入小唄集』(大正2年11月 実業之日本社)が、
この時代を代表する詩集であると考えられているわけではありません。
竹久夢二の代表詩集であるとみなされているかも、危ういところがあります。
ただ、『どんたく 絵入小唄集』の内容をみれば、夢二の秀作を収録した詩集であることは
認めなくてはならなくなります。夢二が好きな人には親しみやすい詩が、収録されているとも言えます。
exhibition 竹久夢二には、この詩集からいくつかの詩を紹介しました。
宵待草(原詩 明治45年/完成詩 大正2年) 竹久夢二
詩としての「宵待草」とその周辺のことについては、既にまとめています。しかしながら、実のところ、『どんたく 絵入小唄集』については、ほとんど切り込むことができていません。(注1)
ですが、代表詩「宵待草」をはじめとする夢二の詩とは何だったのかについて探求をすすめていくにあたり、収録詩集の位置づけを考えてみる必要はあるはずなのです。
『どんたく 絵入小唄集』は、題名にそえてあるように詩を収めたなかに、夢二自身の絵が入っています。しかしながら、他の夢二著書の多くが著者自らの装幀であることが多いのに、この詩集は、年若い友人である恩地孝四郎によって装幀されています。
夢二の本と言えば、明治期の終わりに出された『夢二画集』のシリーズを思う人が少なくないように、彼はコマ絵に独特の境地を開いた画家でした。大正期に入ってからも、夢二著だけではなく編・プロデュースのものから他者の書著や子供向けのものまで、夢二挿絵・装幀の本は多種多様に出されています。可憐にして美麗な書物の世界が繰り広げられているのです。
『どんたく 絵入小唄集』は、夢二にとって重要な本であるはずなのに、いくらか遊びの余裕をもって若い恩地に装幀を任せたと考えられるかも知れません。ほとんど同時期にだされた『昼夜帯』のほうが、表紙も挿入画も夢二であり、内容的にも短歌や短詩などが集約されていて、夢二の作品集としてまとめられたようにみうけられます。
夢二の創作世界にはたくさんの引き出しがありすぎるために、代表作・代表詩集ということを考えるといくつもの答えがでてくるようです。
さらに、明治後半から大正期は、まさに詩の時代でした。詩集は特に優れた美意識で装幀されるのが常で、明治後期には、詩画集の概念もすでに登場していました。こういう時代背景のなかで、夢二は詩人としての才能も発揮したのでした。無論、一般的に言っても、詩人に絵心がある人は少なくありません。
このような時代に、まず、『夢二画集』のシリーズは、進化した詩画集として企画されたとも考えられます。そして、古謡の採取も明治末から始まっていました。西欧的な長詩だけではなく、短詩・歌、民謡・小唄というものの認識も再開されたのが、この時代でした。彼の詩集『どんたく』が、小唄集としてまとめられたことは、時代を先取りしていたとも考えられるのです。
夢二は何でも先取の人だったということは言われています。大正期の総合性の強い芸術文化の先駆者であり担い手である彼の詩と詩集については、再考する余地があることでしょう。明治末から大正2、3年に上梓された詩と詩集を対象とするいわゆる詩歌史において、『夢二画集』も『どんたく』も『昼夜帯』も、特に触れられてないのは不思議といえばそうなのです。
「宵待草」を詩としても歌謡としても充分に考えてみるなら、まずは、詩集、歌集、古謡集をはじめとする夢二著書をよく見ていかなくてはなりません。そして、明治後期から大正期にかけての詩と詩集についても考察を及ぼすことが望ましくなります。そのような課題に取り組んでいくことができたらと思います。(注2)(2012.1.20)
補注
注1 『「宵待草」ノート 竹久夢二と大正リベラルズ』 (拙著) はる書房 2011 ⇒ Book review
注2 「竹久夢二の童謡風な絵と唄」(拙著)所収『大正・昭和の“童心”と山本有三』 笠間書院 2005
⇒ Book review
夢二編『あやとりかけとり』から、彼の古謡の採取とリライトについて試論したことがあります。
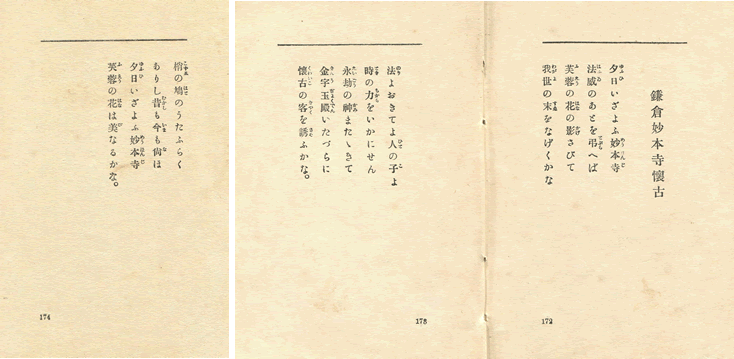
国木田独歩「鎌倉妙本寺懐古」
『独歩詩集』(三木露風 編 岡落葉 装幀 東雲堂書店 大正2年11月)より (個人蔵)
『抒情詩』(明治30年)収録の「独歩吟」そのほかの国木田独歩の詩は、
短編小説の妙手として評価される独歩の死から5年後に、三木露風により編纂されました。
独歩の「山林に自由存す」が後世にひろく伝わる契機となる詩集を、
露風が世に送り出したことになります。
吉江孤雁が書いた序には、独歩自らが、最後の作「妙本寺」の詩を
「桜田本郷の独歩社の二階の、秋の日の当つてゐる縁側で吟誦して」
聴かせてくれたことがあります。口ずさむことのできる詩というものは、
独歩がめざしたもののひとつであったということをうかがえます。
7・5音の連なり
夢二の「宵待草」は、明治末に生み出され、石川啄木の『悲しき玩具』などの三行に書かれた短歌に触れて、大正の初めに、三行詩として集約したと筆者は考えました。夢二は、小唄という言葉を使ってはいますが、一般の小唄は、7・7/7・5の連なりであることの方が多いようで、新体詩以降の詩の流れのうちに、「宵待草」の詩の7・5/7・5/7・5という音の繰り返しはあるのだろうと思いながら、これについては、まだ考察を進めていませんでした。
ふと気づくと、独歩が自ら愛唱したとされる「鎌倉妙本寺懐古」のすべての行は、7・5音になっているのです。大正期の夢二には、「室之津懐古」の画題があることは知られているとおりです。抒情とノスタルジーを表現することに傾注して、音の形式としては、7・5を愛用することを、夢二が独歩を通して学んだ可能性は考えられます。
また、ひとつ思いつくことは、土井晩翠の作詩した「荒城の月」もまた、7・5音の連なりで成っています。これは、明治34年に中学校唱歌として作詩され、滝廉太郎作曲・山田耕作編曲で知られています。大正期にセノオ楽譜としてだされていますが、その表紙を夢二が描いています。
夢二の「宵待草」ほか『どんたく』の7・5調の詩の背景には、歌謡の源流としての7・5音からなる明治の詩があったということです。そして、その本格的な普及は、大正期以降のことだったのです。
ちなみに、露風の童謡「赤とんぼ」は、ほぼ8・5音の繰り返しからなっていて、7・5音の連なりに近い形態であるとは言えそうです。(2013.1.23)
また、7・5の繰り返しは、伝統的な流行歌の形式、今様に遡って考えてみる必要はあるかと思われます。「荒城の月」や「われは海の子」(文部省唱歌)は、7・5を4回繰り返していて、今様の踏襲といえそうです。ただ、「宵待草」は、三回の繰り返しであり、夢二の三行詩として考えたいところがあります。(2013.4.9)
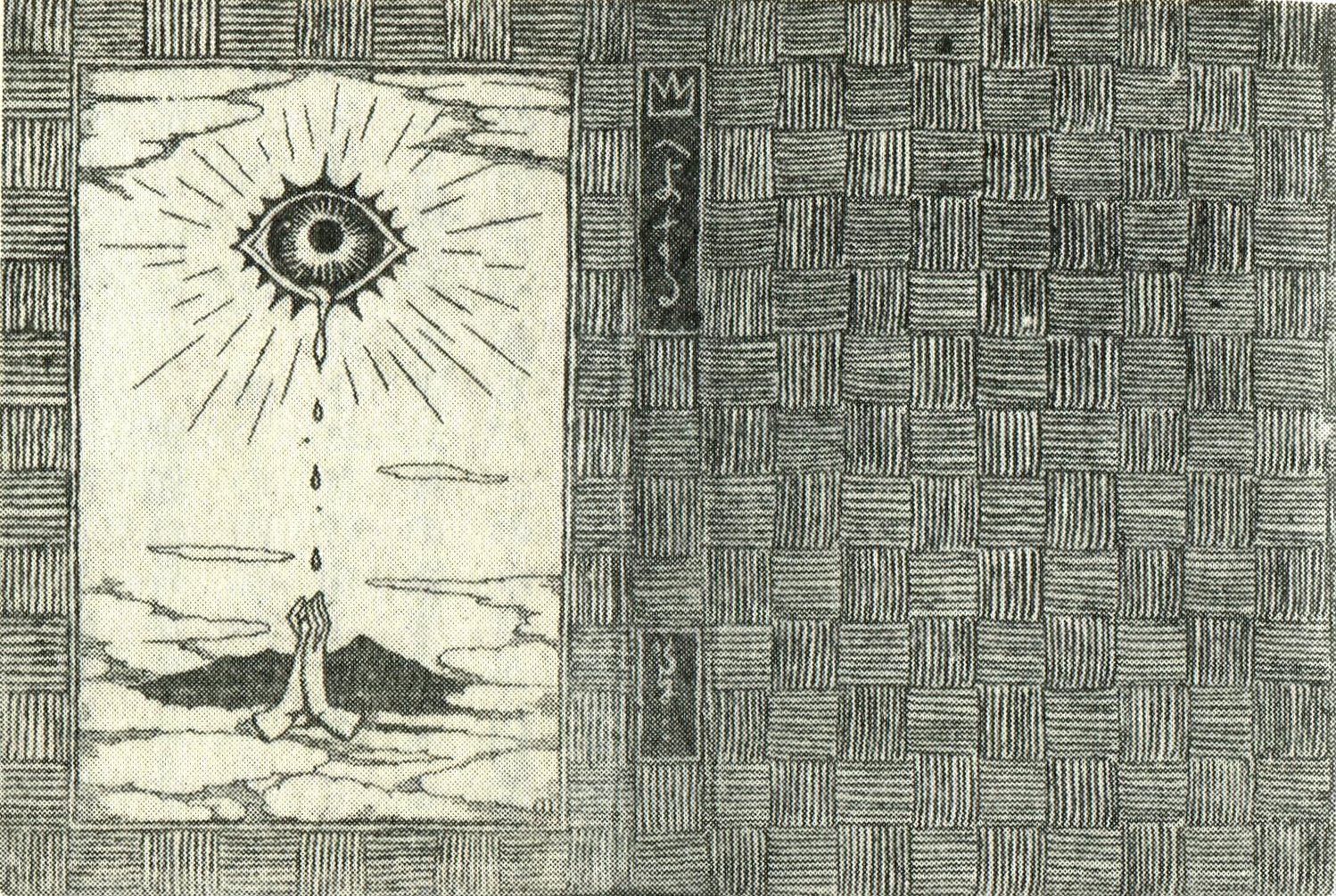
『山へよする』(歌集)竹久夢二著・装幀 新潮社 大正8年
木版による表紙は、目と手を配した夢二特有の構図になっています。
彦乃との恋の逃避行を短歌と挿画で表した歌集で、夢二の代表的著書のひとつです。
高村光太郎の彫刻〈手〉は、美術館のサイトで見ることができます。
光太郎は、彫刻と詩を、別々に創作する方針をとっていましたが、
詩のなかでもしばしば、「手」をうたっています。
「わたくしの手は重たいから / さうたやすくはひるがへらない。」で始まる「月にぬれた手」は、
『典型』(中央公論社 昭和25年)に収められていて、よく知られています。
この詩集により、昭和26年には、第二回読売文学賞を受けました。
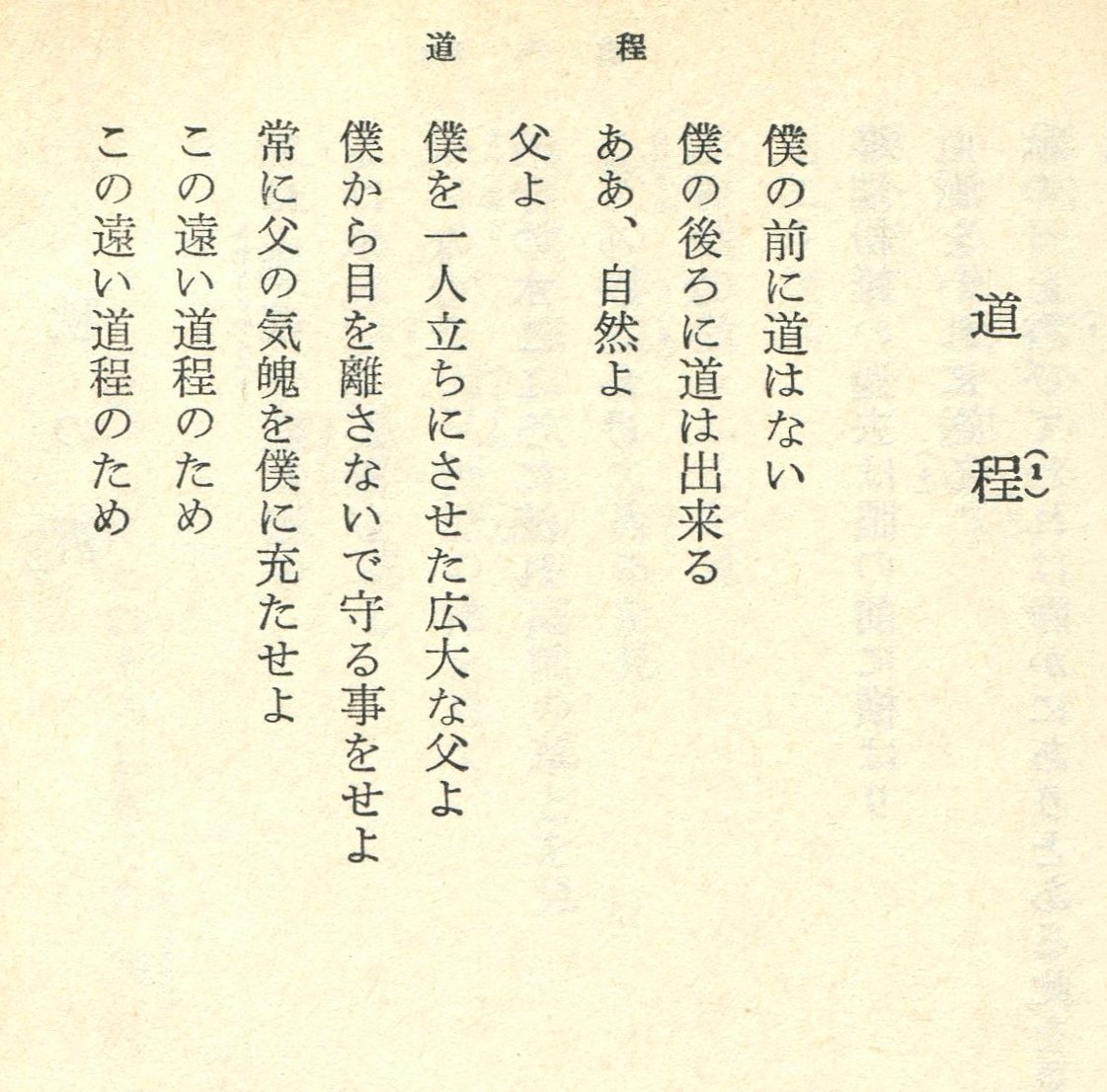
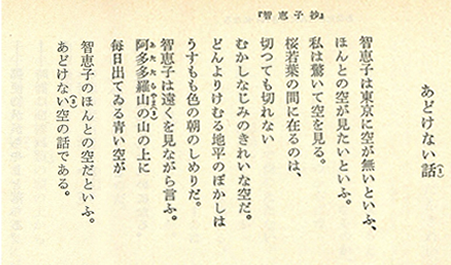
「道程」高村光太郎 『道程』(大正3年 抒情詩社)より 初出は『美の廃墟』(大正3年3月号)
「あどけない話」高村光太郎 『智恵子抄』(昭和16年 竜星閣)より 初出は『東方』(昭和3年6月号)
「道程」詩の道のり
高村光太郎〔1883(明治16)年~1956(昭和31)年〕は、口語自由詩を確立したことで萩原朔太郎と並んで詩史において論じられる詩人です。彼はそもそも彫刻家であったわけですが、造形作家にして詩人だったことにおいては、竹久夢二に通じるところがあります。筆者には、夢二と光太郎は、微妙に異なる詩人であるように感じられます。ただ、抒情画とブロンズというそれぞれの分野が“柔”と“剛”であるのをはじめとして、対照的なところの方が多く、二者の考察には、難しい課題があり、充分に論じるためにの準備は充分であるとはいえません。
光太郎の彫刻〈手〉は、ほとんど誰でもが美術の教科書か美術館においてブロンズ像を見た記憶を持っているはずです。それに対して、ほぼ同じ時期に夢二が手をよく描いたことは、夢二の愛好家でなくては知らないことではないでしょうか。印相のように手によって何か宗教的思想が表されているように見る人もいるでしょうし、手による芸術や技が見直された時代に表現された“手”について考える課題もあります。
両者の詩については、夢二の「宵待草」も、光太郎の「道程」も、当初発表された原詩とは違う、ごく短い形態で完成されたことが注目されます。近代芸術の簡潔なあり方ということでしょうか。ですが、「宵待草」は、8行詩が3行詩となったのに対して、「道程」は、当初は102行あったのが、9行となっています。少し桁違いということはあります。
夢二は、創作モチーフとしてのマツヨイグサなり月見草を愛していました。しかしながら、すでに『夢二画集 夏の巻』の表紙絵にマツヨイグサを配したこともあり、「宵待草」を冠した詩集を出すことはありませんでした。そして、この詩は、曲がつけられて歌われるようになったために、草の根的に広まって行ったのです。
光太郎の『道程』は、彼の最初の詩集であり、それに相応しい詩を題名に冠しています。そして、この「道程」は、『日本少国民文庫 巻16 日本文学選』(山本有三選 新潮社 昭和11年)に収録され、やがて教科書にも掲載されるようになります。
あえて言えば、「宵待草」は、サブカルチュアとして多くの人々に愛される歌となり、「道程」は、ハイカルチュアを志向する文学として青少年の教材ともなったとみることができます。享受の形態は、作者が選ぶものとは限りませんが、そこに作者の姿勢が何らかのかたちで間接的にかかわっているとは考えることができます。
夢二が体験し表現もした悲恋と、光太郎が智恵子を狂気に奪われたことは、彼らの世代における自由恋愛の実態を伝えています。ただ、新しく自由な関係を望みながら、夢二は作品に映すばかりで女性をいつも逃し、光太郎は智恵子を配偶者として生涯も創作も捧げる結果になっています。生き様と個性の違いは明らかです。
このように概観してゆくと、伝承的な小唄や定型詩と、現代につながる口語自由詩の世界は、別々に語ってはどうかと言われそうです。それぞれの作者である夢二と光太郎を比べなくてはならない理由は何なのか、そういう問いに立ち戻ってしまいそうです。
これに対しては、大正期の詩人を考えるにあたり、分類でことが足りるのではなく、どうしてもこの二人が気にかかるのだと繰り返すほかありません。明治生まれの詩人を顧みる意味で、『独歩詩集』の序をまた開いてみましょう。吉江孤雁は、独歩を、さまざまなことをした人であったけれども、何よりも詩人であることにこだわった人であるという意のことを書いています。
光太郎は、自分は彫刻家であると言っていました。夢二は、自分の詩はパンの代わりにはならないと言って画家、技術家の立場をとっていました。詩は、本業・生業ではないという意味においては同様です。独歩も、小説家、編集者として認める人はいても、詩が本業であるとは見られていませんでした。たまたま、詩を本業・生業としないケースが揃いました。ですが、ただ、彼らは、本質的に詩人であったかもしれないと思われるのです。
本質的に詩人というのは、絵で詩を描いた夢二についていわれていることですが、独歩の詩人へのこだわりも、本質的に詩人であることを大切にしていたということではなかったでしょうか。光太郎も、本来、詩人ではあったのですが、彫刻家である運命を受け入れていたように考えられるのです。
本質的な詩人というのは、たまたま詩を書いた、職業的に従事したというのではなく、自らの資質により自覚的に詩を書いたということだと思います。また、しばしば言われたような、恋愛と失恋から詩を生み出す人であったことも、再考しなくてはならない課題となります。近代から現代の詩のアンビバレンツな道程を思うとき、詩人としての自覚とためらいの強かった作家として、独歩の次には、夢二と光太郎が、迫ってくるのです。(2013.6.14)
参考図書
『高村光太郎詩集』北川太一編 高村記念会 旺文社 1992年